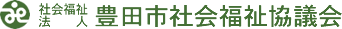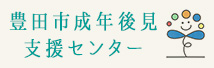令和7年度 事業計画及び予算
令和6年度 事業計画及び予算
令和5年度 事業計画及び予算
社会福祉協議会(社協)とは
-
- 社会福祉法第109条に規定された社会福祉法人で、当該地域における社会福祉の推進を
図るため、地域住民と協働して、すべての人々が互いに助け合い、安全で安心して暮らす
ことができるぬくもりのあるまちづくりを目指す「公共性」「公益性」の高い民間組織です。
- 社会福祉法第109条に規定された社会福祉法人で、当該地域における社会福祉の推進を
-
- 全国、都道府県、市町村に設置され、そのネットワークを活かした活動をしています。
-
- 社会福祉協議会のことを、略して「社協(しゃきょう)」といいます。
-
- 豊田市社協の目的に賛同いただく会員として、「普通、賛助、法人、団体、施設」の5区分
でご協力いただいています。
- 豊田市社協の目的に賛同いただく会員として、「普通、賛助、法人、団体、施設」の5区分
理念・経営方針
理 念
私たちは、地域住民と協働して社会福祉事業を進め、子供から高齢者まで
すべての人々がともに助け合い、安全で安心して暮らすことができる
ぬくもりのあるまちづくりをめざします。
経営方針
福祉関係者との連携を密にし、積極的に地域福祉を推進します。
愛と思いやりをもって質の高い福祉サービスを提供します。
住民(会員)の期待に応えられるよう提案型の事業経営を行います。
職員の行動指針
住民から信頼される社会福祉の専門家をめざします。
利用者の立場に立って行動するよう努めます。
自らの業務に誇りと責任をもって前向きに取り組みます。
社会情勢の変化に対応できるよう自己研鑽に努めます。
ボランティア精神を養い社会貢献に努めます。
役員名簿
| 役職 | 氏 名 | 所属等 | 選出区分 |
| 会 長 | 安田 明弘 | 豊田市社会福祉協議会 | 社会福祉事業について識見を有する者 |
| 副会長 | 高村 伸一 | 豊田市区長会 | 住民組織の代表者 |
| 理 事 | 大石 智里 | 豊田市議会 | 福祉に関する実情に通じている者 |
| 理 事 | 山岡 正博 | 豊田商工会議所 | 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 |
| 理 事 | 水野 智弘 | 豊田市福祉部 | 社会福祉事業について識見を有する者 |
| 理 事 | 三﨑 祐子 | 豊田市ファミリー・サービス・クラブ | 民間社会福祉団体の代表者 |
| 理 事 | 安井 良法 | 豊田市民生委員児童委員協議会 | 民生委員児童委員 |
| 理 事 | 矢頭 功生 | 豊田東ロータリークラブ | ボランティア団体の代表者 |
| 理 事 | 福岡 守男 | 豊田南ライオンズクラブ | ボランティア団体の代表者 |
| 理 事 | 八鍬 幸雄 | ボランティアセンター運営委員会 | 福祉に関する実情に通じている者 |
| 理 事 | 尾形 義孝 | 小原支所地域代表 | 住民組織の代表者 |
| 理 事 | 山口 光岳 | 下山支所地域代表 | 住民組織の代表者 |
| 常務理事 | 後藤 哲也 | 豊田市社会福祉協議会 | 社会福祉事業を行う団体の役職員 |
| 監 事 | 竹内 未帆 | 豊田市総務部 | 社会福祉事業について識見を有する者 |
| 監 事 | 鈴木 康生 | 東海税理士会豊田支部 | 財務管理について識見を有する者 |
(令和7年6月26日現在)
豊田市社協のおもな構成
役員等
・役員 / 理事13名・監事2名
・評議員28名
・組織…社会福祉施設、社会福祉関係団体、ボランティア、その他の社会福祉関係者及び学識経験者をもって組織しています。
定款
○ 定 款
制定昭和50年8月29日認可
第1章 総則
(目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、豊田市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
(2) 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
(3) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
(4) (1)から(3)のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
(5) 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡
(6) 共同募金事業への協力
(7) 福祉サービス利用援助事業
(8) 老人居宅介護等事業の経営
(9) 老人デイサービス事業の経営
(10) 身体障害者福祉センターの経営
(11) 障害福祉サービス事業の経営
(12) 特定相談支援事業の経営
(13) 障害児相談支援事業の経営
(14) 地域活動支援センター事業の経営
(15) 生活福祉資金貸付事業
(16) 福祉相談等事業
(17) 養育支援訪問事業
(18) 老人福祉センターの経営
(19) ボランティアセンター事業
(20) 地域ふれあいサロン事業の推進
(21) その他この法人の目的達成のため必要な事業
(名称)
第3条 この法人は、社会福祉法人豊田市社会福祉協議会という。
(経営の原則)
第4条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的に経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図るものとする。
2 この法人は、住民や福祉関係者等とともに地域の福祉課題・生活課題の解決に取り組み、支援を必要とする者に無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
第5条 この法人の事務所を、愛知県豊田市錦町1丁目1番地1に置く。
第2章 評議員
(評議員の定数)
第6条 この法人に評議員20名以上28名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第7条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、事務局員1名、外部委員2名の合計3名で構成する。
3 評議員選任・解任委員の選任及び解任は、理事会において行う。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案は、別に定める規程に基づき理事会が行う。
5 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
6 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選任・解任委員会の運営についての規程は、理事会において定める。
(評議員の資格)
第8条 社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(評議員の任期)
第9条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第6条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第10条 評議員に対して、各年度の総額が150万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第3章 評議員会
(構成)
第11条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第12条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 予算及び事業計画の承認
(5) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録並びに事業報告の承認
(6) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
(7) 定款の変更
(8) 残余財産の処分
(9) 基本財産の処分
(10) 社会福祉充実計画の承認
(11) 公益事業に関する重要な事項
(12) 解散
(13) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 評議員会の議長は、その都度評議員の互選とする。
(決議)
第16条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第18条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第17条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2人は、前項の議事録に記名押印する。
第4章 役員
(役員の定数)
第18条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上13名以内
(2) 監事 2名
2 理事のうち1名を会長、1名を副会長、1名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって社会福祉法の理事長とし、常務理事をもって同法第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第19条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員の資格)
第20条 社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 会長及び常務理事は、毎会計年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
3 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第5章 理事会
(構成)
第26条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては会長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第28条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(議長)
第29条 理事会の議長は、その都度理事の互選とする。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 会員
(会員)
第32条 この法人に会員を置く。
2 会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。
3 会員に関する規程は、評議員会において別に定める。
第7章 委員会
(委員会)
第33条 この法人に委員会を置く。
2 委員会は、専門的事項について、この法人の運営に参画し、或いは会長の諮問に答え、又は意見を具申する。
第8章 事務局及び職員
(事務局及び職員)
第34条 この法人の事務を処理するため事務局を置く。
2 この法人に、事務局長を1名置くほか、職員を置く。
3 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
4 施設長等以外の職員は、会長が任免する。
5 事務局及び職員に関する規程は、別に定める。
第9章 資産及び会計
(資産の区分)
第35条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産及び公益事業用財産の3種とする。
2 基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
現金、預金及び有価証券3億6千6百万円
3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産は、第43条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。
(基本財産の処分)
第36条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て、豊田市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、豊田市長の承認は必要としない。
(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る)
(資産の管理)
第37条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、会長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第38条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第40条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第41条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第42条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。
第10章 公益を目的とする事業
(種別)
第43条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、次の事業を行う。
(1) 豊田市の福祉センターの経営
(2) 豊田市障がい者総合福祉会館の経営
(3) 豊田市介護予防拠点施設の経営
(4) 豊田市地域包括支援センター事業
(5) 豊田市地域生活支援事業
(6) 豊田市生活困窮者自立支援事業
(7) 豊田市成年後見支援センター事業
(8) 居宅介護支援事業
(9) 無料職業紹介事業
2 前項の事業の運営に関する重要な事項については、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意を得、評議員会の承認を得なければならない。
第11章 解散
(解散)
第44条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第45条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
第12章 定款の変更
(定款の変更)
第46条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、豊田市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を豊田市長に届け出なければならない。
第13章 公告の方法その他
(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、社会福祉法人豊田市社会福祉協議会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞、この法人の機関紙又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第48条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
この法人の設立当初の役員、評議員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
|
会長
副会長 常務理事 理事 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 監事 〃 |
宇野長男
寺沢藤一 石川忠次 鈴木喜一 成瀬清男 竹内正和 竹内三二 中山三郎 永田安衛 今井日吉 伊与田潜 安田政四 藤井利平 寺田勝一 山田義雄 青山文雄 本多貴美子 簗瀬博一 篠田邦雄 浦野釟男 岡田薫 |
附 則
この定款は、豊田市長の認可のあった日から施行する。
附 則
この定款は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この定款は、令和5年4月1日から施行する。
現況報告書および決算書について
平成29年度より「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」にて公表しています。
平成28年度決算書について
現況報告書・決算書について
平成28年度現況報告書
平成27年度決算書
| 一般会計 | 公益特別会計 |
| 事業活動計算書 PDF:37KB | 事業活動内訳表 PDF:43KB |
| 貸借対照表 PDF:93KB | 貸借対照表内訳表 PDF:86KB |
会員規則
(平成4年3月23日規則第5号)
(目的)
第1条 この規則は、定款第32条第3項の規定に基づき、会員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会員)
第2条 この規則において「会員」とは、原則として豊田市内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び豊田市内において事業若しくは活動を行う個人又は法人その他の団体で、社会福祉法人豊田市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の目的に賛同し、入会したものをいう。
2 本会の会員の区分は、次のとおりとする。
(1)普通会員
(2)賛助会員
(3)施設会員
(4)団体会員
(5)法人会員
(会員証)
第3条 本会会長は、会員に会員証を交付するものとする。
(会員への義務)
第4条 本会は、会員に対し次の事項を実施するよう努めなければならない。
(1)毎年度の予算、決算及び事業の報告
(2)本会の発刊、発行する機関紙、パンフレット、ちらし等の配布
(3)本会の発刊する社会福祉関係資料、その他の資料の配布
(4)本会の実施する各種調査の結果報告
(5)本会の実施する大会、講習会、研修会等への参加案内
(会費)
第5条 会員の会費額は、次の各号に掲げる会員の区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。
(1)普通会員 1世帯当たり年額300円以上1,000円未満
(2)賛助会員 1世帯当たり年額1,000円以上
(3)施設会員 1施設当たり年額2,000円
(4)団体会員 1団体当たり年額2,000円
(5)法人会員 1口当たり年額3,000円
2 前項の規定にかかわらず、300円未満の納入にあっては、これを協力費として会費額に算入するものとする。
(会員の義務)
第6条 会員は、その年度の会費を定められた期間内に納入しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、本会会長が別に定める。
付 則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 会員規程(昭和58年規程第13号)は、廃止する。
付 則
(平成20年9月24日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則
(平成22年3月24日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付 則
(平成30年4月1日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
情報公開規則
情報公開規則
(平成13年9月27日 規程第5号)
(目的)
第1条 この規則は、豊田市情報公開条例(平成10年豊田市条例第34号。以下「条例」という。)第26条第1項の規定に基づき、社会福祉法人豊田市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の保有する文書の開示の推進に関し必要な事項を定めることにより、本会の行う事業について市民の理解と信頼を確保し、公正で開かれた本会の運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「文書」とは、本会の職員(役員を含む。以下同じ。)が平成11年4月1日以後に職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録で本会が定めるものをいう。以下同じ。)であって、本会の職員が組織的に用いるものとして、本会が保有しているものをいう。
(本会の責務)
第3条 本会は、この規則の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この規則の定めるところにより文書の開示を申し出ようとするものは、条例の趣旨にのっとり、適正な申出に努めるとともに、文書の開示により得た情報を適正に使用しなければならない。
(文書の開示の申出)
第5条 次に掲げるものは、本会に対し、文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する具体的利害関係に係る文書の開示に限る。)を申し出ることができる。
(1)市内に住所を有する者
(2)市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3)市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4)市内に存する学校に在学する者
(5)前各号に掲げるもののほか、本会が行う事務又は事業に具体的利害関係を有するもの
(開示の申出の手続)
第6条 前条の規定による文書の開示の申出(以下「開示申出」という。)は、書面(以下「開示申出書」という。)を本会に提出しなければならない。なお、開示申出書の様式は、別に定めるとおりとする。
2 本会は、開示申出書に形式上の不備があると認めるときは、開示申出をしたもの(以下「開示申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができるものとし、開示申出者が当該補正を行わないときは、当該開示申出に応じないことができる。
(開示申出書の受付)
第7条 開示申出書の受付は、本会総務課において行う。
(文書の原則開示)
第8条 本会は、開示申出があったときは、開示申出に係る文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示申出者に対し、当該文書を開示するものとする。
(1)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項においても同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により、又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活、財産又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。ただし、豊田市から本会に派遣されている者を除く。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職名及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分であって、公にすることにより、当該公務員の権利利益が不当に害されるおそれがないと認められるもの
(2)法人その他の団体(豊田市及び本会を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活、財産又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。
イ 本会の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3)公にすることにより、人の生命、健康、生活、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(4)本会並びに国、豊田市及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思志決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5)本会が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他の当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、本会、国、豊田市又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(6)法令等の規定により、公にすることができないと認められる情報
(文書の部分開示)
第9条 本会は、開示申出に係る文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示申出者に対し、当該部分を除いた部分につき文書の開示をするものとする。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 開示申出に係る文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(文書の存否に関する情報)
第10条 開示申出者に対し、当該開示申出に係る文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、本会は、当該文書の存否を明らかにしないで、当該開示申出を拒否するものとする。
(開示申出の拒否)
第11条 本会は、開示申出が不当な目的によることが明らかなとき又は文書の開示により知り得た情報を不当な目的に使用されるおそれがあることその他の当該開示申出を拒否するに足りる相当な理由があると認めるときは、当該開示申出を拒否することができる。
(開示申出に対する措置)
第12条 本会は、開示申出に係る文書の全部又は一部の開示をするときは、その旨の決定をし、開示申出者に対し、遅滞なく、当該決定の内容を書面により通知するものとする。ただし、当該決定の内容が開示申出に係る文書の全部の開示をする旨であって開示申出の提出があった日に文書の開示をするときは、口頭により通知することができる。
2 本会は、開示申出に係る文書の全部を開示しないとき(第10条及び前条第1項の規定により開示申出を拒否するとき並びに開示申出に係る文書を保有していないときを含む。)は、文書の開示をしない旨の決定をし、開示申出者に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
第13条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示申出があった日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、本会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を当該期間の満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、本会は、開示申出者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(第三者に関する情報に係る意見の聴取等)
第14条 本会は、開示申出に係る文書に本会及び開示申出者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示決定等をするに当たって、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
(文書の開示の方法)
第15条 文書の開示は、本会が第12条第1項の規定による通知の際に指定する日時及び場所で行うものとする。
2 本会は、文書の開示をすることにより、当該文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めたとき、第9条の規定により文書の一部を開示するときその他合理的な理由があるときは、当該文書の写しにより文書の開示をすることができる。
3 電磁的記録の文書の開示は、本会が定める方法により行うものとする。
(他の制度との調整)
第16条 この規則の規定は、法令等の規定により文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合においては、適用しない。
(費用の負担)
第17条 この規則による文書の開示申出は、無料とする。
2 この規則による文書の写しの交付をうけるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(異議の申出)
第18条 開示申出者は、開示決定等について不服があるときは、本会に対し、次に掲げる事項を記載した書面により異議の申出(以下「異議申出」という。)をすることができる。
(1)異議申出をする者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2)異議申出に係る開示決定等の内容
(3)異議申出に係る開示決定等があったことを知った年月日
(4)異議申出の趣旨及びその理由
2 異議申出は、開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。
3 第1項の異議申出があった場合は、本会は、当該異議申出に係る開示決定等について、情報公開に関し優れた識見を有する者の意見を聴いた上で再度の検討を行い、異議申出者に対し、その結果を書面により回答するものとする。
(情報提供の推進)
第19条 本会は、市民が本会に関する情報を適時に、かつ、容易に得られるよう情報提供の推進に努めるものとする。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、本会会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成16年9月21日規程第9号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日規程第49号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年9月18日規程第35号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成30年6月1日規程第47号)
この規程は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(令和3年6月1日規則第43号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和6年6月1日規則第3号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画(第4回)
職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、下記の行動計画を策定します。
1 計画期間 2023年12月1日~2028年11月30日までの5年間
2 内 容
目標1 人事労務、制度に係る職員の認知を深め、利用の促進を図ります。
対策
・2024年4月~ 所属長、担当者への労務、制度に係る説明会を実施する。
・2024年8月~ 育児休業等の取得対象である男性職員に対し、関係する休暇や制度等を個別に説明する。
・2024年10月~ 社内通知やメールにより定期的に職員に情報提供を行う。
目標2 働き方に関する職員の意識改革に取り組みます。
対策
・2023年12月~ ノー残業デー実施の周知を図る。
・2024年4月~ 各部署において年次有給休暇の取得計画を策定する。
・2024年5月~ 有給休暇の取得促進として、ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等と併せて年次有給休暇の連続取得を推奨する。
目標3 ICT、在宅ワーク等の導入により業務の効率化を図ります。
対策
・2024年4月~ 対象業務や対象者、ルール等について検討する。
・2025年4月~ 試行実施し、課題を分析・対策する。
・2026年4月~ 本格導入。
ソーシャルメディア運用方針等
プライバシーポリシー
社会福祉法人豊田市社会福祉協議会は、以下の方針に基づき、個人情報の保護に努めます。
1.本会は、個人の人格尊重の理念のもとに、関係法令等を遵守し、実施するあらゆる 事業において、個人情報を慎重に取り扱います。
2.本会は、個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。
3.本会は、個人情報の利用目的をできる限り特定するとともに、その利用目的の範囲でのみ個人情報を利用します。
4.本会は、あらかじめ明示した範囲及び法令等の規定に基づく場合を除いて、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく外部に提供しません。
5.本会は、個人情報を正確な状態に保つとともに、漏えい、滅失、き損などを防止するため、適切な措置を講じます。
6.本会は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停止を求める権利を有していることを確認し、これらの申出があった場合には速やかに対応します。
7.本会は、個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ速やかに対応します。
8.本会は、個人情報を保護するために適切な管理体制を講じるとともに、役職員の個人情報保護に関する意識啓発に努めます。
9.本会は、この方針を実行するため、個人情報保護規程を定め、これを本会役職員に周知徹底し、確実に実施します。
個人情報保護規則
個人情報保護規則
(令和6年6月1日規則第4号)
個人情報保護規則(平成16年9月21日規程第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 個人情報の取得、利用(第4条~第8条)
第3章 個人データの安全・適正な管理(第9条~第14条)
第4章 個人データの漏えい等の報告(第15条)
第5章 個人データの第三者提供の制限(第16条~第18条)
第6章 本人関与のしくみ(第19条~第28条)
第7章 苦情の解決(第29条~第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、社会福祉法人豊田市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が保有する個人情報等の取扱いについての基本的事項を定め、個人の権利利益の保護及び人格の尊重を図るとともに、事業の適正な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画、電磁的記録に記載もしくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(2)個人識別符号が含まれるもの
2 この規則において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号をいう。
(1)特定の個人の身体の特徴(DNA、容貌、声帯、指紋等)を電子計算機の用に供するために変換した符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
(2)対象者ごとに異なるものとなるように役務の利用もしくは商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカード等の書類に記載された番号その他の符号であって、特定の利用者もしくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの(旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、個人番号、被保険者証番号等)
3 この規則において「要配慮個人情報」とは、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する個人情報であって、次の各号のいずれかの記述等が含まれるものをいう。
(1)本人の人種、信条又は社会的身分
(2)病歴
(3)身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があること
(4)本人に対して医師等により行われた健康診断その他の検査の結果
(5)犯罪の経歴又は犯罪により害を被った事実
(6)本人を被疑者又は被告人として、刑事事件に関する手続きが行われたこと
(7)本人を、罪を犯した少年又はその疑いのある少年として、少年の保護事件に関する手続きが行われたこと
4 この規則において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものを除く。)をいう。
(1)特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
(2)前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
5 この規則において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。
6 この規則において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
7 この規則において「保有個人データ」とは、本会が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして次の各号に掲げるもの以外のものをいう。
(1)当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれのあるもの
(2)当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
(3)当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国もしくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
(4)当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
8 この規則において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(本会等の責務)
第3条 本会は、この規則の目的を達成するため、個人情報等の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 本会の役職員及び本会の定款に定められた委員会の委員(以下「職員等」という。)は、職務上もしくは活動上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
第2章 個人情報の取得、利用
(利用目的の特定)
第4条 本会は、個人情報を取り扱うにあたっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 本会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的による制限)
第5条 本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2 本会は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
3 前2項の規定は、次の各号に掲げる場合については、適用しない。
(1)法令、条例又はこれらに基づく行政通知等(以下「法令等」という。)に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令等の定める事務を遂行することに対して本会が協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(取得の制限)
第6条 本会は、個人情報を取得するときは、個人情報を取り扱う事業の目的を明確にし、当該事業の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
2 本会は、次の各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令等の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5)当該要配慮者個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、出版、報道等により公にされているとき。
(6)本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得するとき。
(7)第16条第2項各号に掲げる場合において、個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき。
3 本会は、個人情報を収集するとき(前項の規定により要配慮個人情報を取得する場合を除く。)には、本人から取得しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1)本人の同意があるとき。
(2)法令等に定めがあるとき。
(3)出版、報道等により公にされているとき。
(4)個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5)所在不明、その他の事由により、本人から取得することができないとき。
(6)争訟、選考、指導、相談等の事業で本人から取得したのではその目的を達成し得ないと認められるとき、又は事業の性質上本人から取得したのでは事業の適正な執行に支障が生じると認められるとき。
(取得に際しての利用目的の通知等)
第7条 本会は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
2 本会は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3 本会は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
4 前3項の規定は、次の各号に掲げる場合については、適用しない。
(1)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本会の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令等の定める事務を遂行することに対して本会が協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(不適正な利用の禁止)
第8条 個人情報は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用してはならないものとする。
第3章 個人データの安全・適正な管理
(データ内容の正確性の確保等)
第9条 本会は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
(安全管理措置)
第10条 本会は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(職員等の監督)
第11条 本会は、職員等に個人データを取り扱わせるにあたっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、職員等に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(委託先の監督)
第12条 本会は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(委託等に伴う措置)
第13条 本会は、委託を受けた者を監督するにあたっては、個人情報の保護に関し次の各号に定める措置を講じなければならない。
(1)再委託の禁止
(2)第三者への提供の制限
(3)委託された事業以外への使用の禁止
(4)複写及び複製の制限
(5)秘密保持の義務
(6)返還及び廃棄の義務
(7)事故発生時における報告の義務
(受託者等の責務)
第14条 本会から個人情報を取り扱う事業を受託した者は、前条に基づき個人情報の漏えい、滅失及びき損防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 前項の受託事業に従事している者又は従事していた者は、その事業に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第4章 個人データの漏えい等の報告等
(漏えい等事案の報告及び本人への通知)
第15条 本会は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして、次の各号に掲げる漏えい等事案が生じたときは、法令の規定に従い、当該事態が生じた旨その他の事項を個人情報保護委員会に報告する。
(1)要配慮個人情報が含まれる個人データ(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。)の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
(2)不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
(3)不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
(4)個人データに係る本人の数が1,000人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
2 本会は、前項に規定する漏えい等事案が生じたときは、法令の規定に従い、当該事態が生じた旨その他の事項を本人に通知する。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
第5章 個人データの第三者提供の制限
(第三者提供の制限)
第16条 本会は、次の各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
(1)法令等に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令等の定める事務を遂行することに対して本会が協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
(1)本会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合
(2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
(3)特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
3 本会は、前項第3号に規定する個人データの管理について責任を有する者の氏名、名称及び住所又は法人にあってはその代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
(第三者提供をする際の記録)
第17条 本会は、個人データを第三者に提供したときは、次の各号に掲げる事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が前条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)前条第1項の本人の同意を得ている旨
(2)当該第三者の氏名又は名称その他の当該第三者を特定するに足りる事項(不特定かつ多数の者に対して提供したときは、その旨)
(3)当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
(4)当該個人データの項目
2 前項の記録は、個人データを第三者に提供した都度、速やかに作成しなければならない。
3 第1項の記録は、その作成日から3年間保存しなければならない。
(第三者提供を受ける際の確認及び記録)
第18条 本会は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、次の各号に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が第16条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名
(2)当該第三者による当該個人データの取得の経緯
2 前項第1号に掲げる事項の確認は、個人データを提供する第三者から申告を受ける方法その他の適切な方法により行い、前項第2号に掲げる事項の確認は、個人データを提供する第三者から当該第三者による当該個人データの取得の経緯を示す契約書その他の書面の提示を受ける方法その他の適切な方法により行う。
3 本会は、前項による確認を行ったときは、次の各号に掲げる事項に関する記録を作成しなければならない。
(1)本人の同意を得ている旨(個人情報取扱事業者以外の第三者から個人データの提供を受けた場合を除く。)
(2)第1項各号に掲げる事項
(3)当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
(4)当該個人データの項目
4 前項の記録は、第三者から個人データの提供を受けた都度、速やかに作成しなければならない。
5 第3項の記録は、その作成日から3年間保存しなければならない。
第6章 本人関与のしくみ
(保有個人データに関する事項の公表等)
第19条 本会は、保有個人データに関し、次の各号に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
(1)本会の名称及び住所並びに代表者の氏名
(2)すべての保有個人データの利用目的(第7条第4項第1号から第4号までに該当する場合を除く。)
(3)第21条第1項、第27条第1項又は第28条第1項もしくは第2項の規定による求めに応じる手続(第23条第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)
(4)保有個人データの安全管理のために講じた措置(本人の知り得る状態に置くことにより当該保有個人データの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。)
(5)保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
2 本会は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
(2)第7条第4項第1号から第4号までに該当する場合
(3)本会は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(開示の請求)
第20条 本人は、本会に対し、当該本人が識別される保有個人データについて、次の各号に掲げるいずれかの方法による開示を請求すること(以下「開示請求」という。)ができる。
(1)電磁的記録の提供による方法
(2)書面の交付による方法
2 保有個人データの開示請求は、本人に代わって、未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人、又は開示請求をすることにつき本人が委任した代理人によって行うことができる。
(開示)
第21条 本会は、前条第1項の規定による保有個人データの開示請求を受けたときは、本人に対し、第25条に定める方法もしくは前項の規定により当該本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
(1)法令等の定めるところにより本人に開示することができないと認められるとき。
(2)個人の評価、診断、判断、選考、指導、相談等に関する保有個人データであって、開示することにより、事業の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるとき。
(3)調査、争訟等に関する保有個人データであって、開示することにより、事業の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるとき。
(4)開示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(5)関係機関との間における協議、協力等により作成し、又は取得した保有個人データであって、当該機関が開示することに同意しないとき。
(6)未成年者又は成年被後見人の法定代理人による開示請求がなされた場合であって、開示することが当該未成年者又は成年被後見人の利益に反すると認められるとき。
2 本会は、前項の規定による開示請求に係る保有個人データの全部もしくは一部について開示しない旨の決定をしたとき、当該保有個人データが存在しないとき、又は本人が請求した方法による開示が困難であるときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
3 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」という。)以外の法令の規定により、本人に対し第1項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、当該法令の規定に定めるところによる。
4 第16条及び第17条第1項から第2項までの規定は、当該本人が識別される個人データに係る第17条第1項及び第18条第3項の記録(以下「第三者提供記録」という。)について準用する。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。
(1)当該記録の存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
(2)当該記録の存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
(3)当該記録の存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国もしくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
(4)当該記録の存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの。
(開示請求の方法)
第22条 第20条第1項の規定に基づき開示請求をしようとする者は、本会に対して、別に定める保有個人データ開示等請求書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 開示請求をしようとする者は、本会に対して、自己が当該開示請求に係る保有個人データの本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。
3 本会は、本人に対し、開示請求に関し、その対象となる保有個人データ又は第三者提供記録を特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、本会は、本人が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該保有個人データ又は当該第三者提供記録の特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。
4 本会は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることとし、開示請求者が補正を行わない場合には、当該開示請求に応じないことができる。
(手数料)
第23条 本会は、第19条第2項の規定による利用目的の通知又は第20条第1項(第21条第4項において準用する場合を含む。)の規定による開示請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。
2 本会は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。
(開示請求に対する決定)
第24条 本会は、開示請求があった日から原則として14日以内に、開示請求者に対して、開示請求に係る保有個人データの全部もしくは一部を開示する旨の決定又は開示しない旨の決定(第22条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人データが記録された請求対象文書を保有していないときの当該決定を含む。)をするものとする。ただし、第22条第4項の規定により、補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 本会は、前項の決定(以下「開示決定等」という。)をしたときは、開示請求者に対し、遅滞なく保有個人データ開示等決定通知書(様式第2号)によりその旨通知するものとする。
3 本会は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に開示決定等をすることができないと認められる場合には、30日以内に決定するものとする。
4 本会は、第1項の規定により開示請求に係る保有個人データの全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、第2項に規定する書面によりその理由を示すものとする。
5 本会は、開示決定等をする場合において、当該決定に係る保有個人データに本会以外の者との間における協議、協力等により作成し、又は、取得した保有個人データがあるときは、あらかじめ、これらの者の意見を聴くことができる。
(開示の方法)
第25条 保有個人データの開示は、保有個人データが記録された請求対象文書の当該保有個人データに係る部分につき、文書、図画又は写真にあっては閲覧もしくは視聴又は写しの交付により、フィルムにあっては視聴又は写しの交付により、磁気テープ、磁気ディスク等にあっては視聴、閲覧、写しの交付等で適切な方法により行う。
2 前項の視聴又は閲覧の方法による保有個人データの開示にあっては、本会は、当該個人情報が記録された請求対象文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該保有個人データが記録された請求対象文書の写しにより開示することができる。
(保有個人データの存否に関する情報)
第26条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人データが存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、本会は、当該保有個人データの存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(訂正等)
第27条 本人は、本会に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を請求することができる。
2 本会は、前項の規定による訂正等の請求を受けた場合には、その内容の訂正等に関して法令等の規定により特別の手続きが定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
3 本会は、第1項の規定による請求に係る保有個人データの内容の全部もしくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。
(利用停止等)
第28条 本人は、本会に対し、当該本人が識別される保有個人データが第5条もしくは第8条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第6条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。
2 本会は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
3 本人は、本会に対し、当該本人が識別される保有個人データが第16条第1項の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができる。
4 本会は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
5 本人は、本会に対し、当該本人が識別される保有個人データを本会が利用する必要がなくなった場合、当該本人が識別される保有個人データに係る第15条第1項に規定する事態が生じた場合その他当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合には、当該保有個人データ利用停止等又は第三者への提供の停止を請求することができる。
6 本会が前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行うものとする。ただし、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
7 本会は、第1項の規定による請求に係る保有個人データの全部もしくは一部について利用停止等を行ったときもしくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は第3項もしくは第5項の規定による請求に係る保有個人データの全部もしくは一部について第三者への提供を停止したときもしくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
第7章 苦情等の手続き
(苦情の処理)
第29条 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 本会は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。
(理由の説明)
第30条 本会は、第19条第3項、第21条第2項、第27条第3項又は第28条第7項の規定により、本人から求められ又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。
(異議の申出)
第31条 第19条における利用目的を通知しない旨の決定、第21条における開示しない旨の決定、第27条における訂正等を行わない旨の決定又は第28条における利用停止等を行わない旨の決定及び第三者への提供停止を行わない旨の決定について異議があるときは、本人は、本会に対して書面により異議の申出(以下「異議申出」という。)ができる。
2 前項の異議申出は、前項の決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に行わなければならない。
3 第1項の異議申出があった場合は、本会は、当該異議申出のあった日から原則として14日以内に対象となった決定について再度の検討を行なった上で、当該異議申出についての回答を書面により行うものとする。
4 本会は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に異議申出に対する回答を行うことができないと認められる場合には、30日以内に行うよう努めるものとする。
5 第3項及び前項に定める異議申出に対する回答は、別に定める苦情解決に関する規則により行うものとする。
(他の制度との調整等)
第32条 法令等の規定により、本会に対して保有個人データの開示等の請求その他これに類する請求ができる場合は、その定めるところによる。
(委 任)
第33条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則(令和6年6月1日規則第4号)
この規則は、令和6年6月1日より施行する。
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画(第2回)
仕事と家庭生活を両立できる働きやすい職場環境を整備することで、女性職員が就業を継続して能力を十分に発揮し、職業生活を充実させることができるようにするため、下記の行動計画を策定します。
記
1 計画期間 2021年4月1日 ~ 2026年3月31日までの5年間
2 本会における課題 ①男女比率と比較して管理職における女性の占める割合が低い。
②有給取得率が低く、家庭生活との両立が難しい。
3 内 容
目標1
管理職(課長級以上)に占める女性割合を20%以上とします。
対策
・若手の労働者を対象とした仕事と家庭の両立を前提としたキャリアイメージ形成のための研修を実施します。
・管理職候補となる男女社員に対して階層別研修を実施することで、昇進に対する不安を払拭し、管理職登用への意欲を高めます。
目標2
令和8年3月までに、年次有給休暇の取得率を30%以上とし、同時に所定外労働を削減し仕事と家庭を両立できる職場環境の整備をします。
対策
・年次有給休暇の取得状況について所属で管理し、積極的に取得するよう呼びかけます。
・育児短時間勤務制度やフレックスタイム制度について周知を行い、より柔軟な働き方を推進します。
・所定外労働を削減するためノー残業デイの実施を徹底します。
・所定外労働時間について所属で月ごとに管理し、削減に努めるよう呼びかけをします。
・所属内で業務状況について情報共有し、上司による業務の優先順位付けや業務分担の見直し等のマネジメントの徹底により互いに助け合う職場環境を整えます。
4 実施時期 2021年4月1日より実施
女性活躍推進法に基づく情報の公表
女性活躍推進法に基づき,以下の情報を公表します。(2025年5月22日現在)
1 管理職(課長以上)に占める女性労働者の割合
0%
2 男女の平均継続勤務年数の差異
| 全体 | 正規職員 | 特定業務職員 | 限定職員等 | ||
| 女性の平均継続勤務年数 | (A) | 10.4年 | 10.4年 | 6.9年 | 11.0年 |
| 男性の平均継続勤務年数 | (B) | 9.7年 | 15.5年 | 1.0年 | 4.9年 |
| 男女の平均継続勤務年数の差異 | (A/B) | 107.8% | 67.3% | 687.5% | 225.0% |
3 男女の賃金の差異
| 全体 | 正規職員 | 特定業務職員 | 限定職員等 | ||
| 女性の平均年間賃金 | (A) | 1,990,928円 | 4,753,670円 | 4,161,033円 | 1,108,256円 |
| 男性の平均年間賃金 | (B) | 3,294,731円 | 6,317,145円 | 4,943,027円 | 910,336円 |
| 男女の平均年間賃金の差異 | (A/B) | 60.4% | 75.3% | 84.2% | 121.7% |